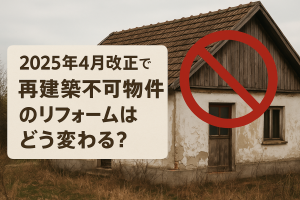
2025年4月改正で「再建築不可物件のリフォーム」はどう変わるのか
■ 改正のポイント
2025年4月の建築基準法改正により、これまで木造2階建て以下の小規模建築物に適用されていた「4号特例」が廃止されました。
その結果、従来は建築確認の省略が認められていた多くのリフォームが、原則として建築確認の対象になっています。
具体的に建築確認が必要になる工事は以下の通りです。
- 大規模修繕:屋根の全面葺き替え、柱や梁の過半数を交換する耐震補強など
- 大規模模様替え:間取り変更で耐力壁を撤去・移設、階段の位置を変更するなど
- 増改築:ロフトやバルコニー増設、延床面積を広げる工事
- 用途変更:住宅を宿泊施設や事務所に用途転換
一方で、クロス張替え、設備交換、外壁塗装など表層的なリフォームは従来通り申請不要です。
■ 再建築不可物件に降りるのか?
最大の問題は、再建築不可物件はそもそも「建替えが認められない」ため、
確認申請の段階で 接道義務や容積率などの要件を満たさず、許可が下りないケースが多いという点です。
つまり、屋根の全面改修や耐震補強といった工事をしようとしても、
「確認申請が必要」→「しかし法的要件を満たせない」→「許可が下りず工事できない」
という事態が実際に起こり得ます。
■ 台風などで屋根が飛んだ場合は?

自然災害による破損でも、屋根の全面葺き替えは大規模修繕扱いとなり、建築確認が必要です。
この場合、確認申請が下りなければ、事実上「屋根がないまま放置」という極端な状況に追い込まれるリスクがあります。
ただし、応急措置や部分的な修繕であれば確認申請不要で進められるため、
現場では「部分修繕にとどめる」「全面交換を小分けに実施する」などの対応が検討されるでしょう。
■ なぜ再建築不可物件をリフォームしにくくしたのか
今回の改正の背景には、以下の意図があると考えられます。
- 耐震性・省エネ性の底上げ
古い住宅の安全性や省エネ性能を、確認審査を通じて担保する狙い。 - 老朽危険建築物の自然淘汰
再建築不可物件を「手直しして使い続ける」よりも、
市場から徐々に退場させ、防災上のリスクを減らす政策的意図。 - 都市再編・土地利用の誘導
不適格な土地利用を減らし、将来的には再開発や道路整備に繋げたいという思惑。
■ まとめ
2025年改正で、再建築不可物件は 「表層リフォームは可能だが、構造に関わる大規模工事は難しい」 という立場にさらに追い込まれました。
自然災害で壊れても「全面修繕できない」リスクがあり、資産価値はますます限定的になります。
裏を返せば、行政としては「再建築不可物件を無理に延命させず、土地を再編へ誘導したい」という明確な方向性を示したとも言えます。
今後この種の物件を扱う際には、“リフォームできる範囲が極めて限定される” ことを前提に、投資判断を行う必要があるでしょう。
